
文化芸術経営のイノベーションを目指して
大局観と座標軸をもとう
基調講演:近藤誠一 氏 国際ファッション専門大学学長 近藤文化・研究所代表 元文化庁長官
日時:2021年6月15日
皆様こんばんは。ヨーロッパの皆様は、こんにちは。ただいまご紹介を頂いた近藤誠一です。今日は、1時間半ほどお時間をいただいて、私の考えている文化と経済の繋ぎ方ということについてお話しをいたしますが、具体的なあるいは技術的、専門的な話というよりは、むしろ私の外交官としてそして文化庁長官としての経験に基づいた大局的なお話しをいたします。皆さんの活動にお役に立てればと思います。
コロナが長引いていることで、皆さんそれぞれがご苦労されていると思います。同時に、この異常な状態というのは、むしろ我々がこれまで道を考えあぐねてきたこと、忘れていたこと、忙しくてゆっくり考える暇がなかったことをじっくり考える機会であるとも言えると思います。後ほどお話しするように、人類の歴史を振り返ってみるとか、そういったことは普段はなかなかできませんが、こういう時だからこそ出来るとも言えると思います。例えば、日本では何かが起こると、文化芸術は不要不急かということが議論になります。そこで、危機に対して文化芸術がどのように対応してきたかについて世界の歴史を振り返ってみます。
例えば14世紀にペストが欧州で流行しました。その時に、ヨーロッパにいらっしゃる方も多いのでご存知かと思いますが、ジョヴァンニ・ボッカッチョの『デカメロン』という小説が書かれています。その内容というのは、フィレンツェに住む、経済的に豊かな男女10人が感染を逃れるために別荘で過ごすという物語です。10日間過ごすわけですが、10人が1日1つ話をする、したがって10日間で100の話ができるわけですね。それが文化史上、画期的な役割を果たしたと言われています。それが、散文で書かれた小説であったからです。それまでは韻文だったわけですね。これによって小説が庶民に広く広まるようになった。つまり、危機を利用して、新たな芸術の形を生み出したということです。
もう一つは美術の世界でも言えることです。それまでは美の表現は大きな壁画などが主流で、動かすことが出来ないもの、例えば建築物などの不動産に大きな芸術性を込めてきた。しかし、そういう場には皆が集まれなくなってしまいました。ペスト感染防止のためです。そうなると、家の中で芸術を楽しみたい、ペストから逃れる時に自分たちで持っていける芸術作品がほしいという、ポータブルな動産的な芸術への需要が高まり、アーティストはそれに応じて、絵画や壺といった作品をつくりました。それもある意味で、ペストという大災難を迎えて、それにアーティストが答える形で、新たな芸術形態を作ったということが言えるわけです。
本日は演劇の方が多いそうですので、もう一つだけ。もともと演劇と言えばギリシャ悲劇が最もオーソドックスな演劇でした。それを超えるものがなかなか出なかった。しかし、16世紀になって、シェイクスピアという人が新しい演劇を作り上げました。ちょうどその頃、ロンドンはペストが大流行し、劇場も一年半近く閉鎖になったと言います。そういう中でシェイクスピアは何をしたと思うでしょうか。ペストをテーマにした戯曲を書いたわけではありません。彼のどの作品をみてもペストらしいものは出てこないですね。彼が気づいたのは、ペストという疫病は、身分、性別、出身、職業を問わず、誰にでも感染する、人は皆もともと平等だ、ということです。ギリシャ神話では、人の運命は神様が全部決めている、それに一生懸命抵抗しようとしたけれど、結局最後は運命から逃れられていないことに気づく、というのがギリシャ悲劇です。しかしシェイクスピアは、いや、一人一人の運命は、予め決まっているわけではなく、一人一人が自分で作る、それによって悲劇も生まれれば喜劇も生まれる、そういう思想で戯曲を書いたわけです。つまり、個人は自由に幸せを求めるものだという前提がそこにはあります。したがって、同じ職業の人々でも、全然違った個性を持つ人物像が登場人物として描かれていることが特徴です。
そんな話もありますので、芸術というのは掴みどころがないようですが、もの凄い力を持っている。ペストという感染症を乗り越える力、むしろ苦難に立ち向かってこそ、底力が発揮される面があるのではないかと思います。今回のコロナも、そういう影響が芸術に生じること、皆さんの活動に、それぞれが反映されることを願っています。
少し前置きが長くなりましたけれども、パワーポイントを用意しましたので、それに沿って進めていきたいと思います。

今文明の中心になっている経済において、文化は中心に置かれていない、その結果、文化が持っている本来の力が発揮できていません。
今日お話することは、先程泉志谷君が言ったようなことですが、現代社会において文化芸術はどういう位置にあるのかということです。まず、現状をどう見るかにあたっては、少し大げさかもしれませんが、宇宙や地球が出来たところから歴史を振り返っていきたいと思います。そして、人間が文明というものを作ってきた歴史の中に、今現在の文化芸術というものを位置づける、ということが、最初のポイントとなります。
歴史の中で様々な問題が生まれました。その一つが、文化芸術を正しく扱っていない、ということです。なぜそうなってしまったのか、ということを、二番目にお話したいと思います。
そして最後に、もう一度人類の歴史に振り返ってみて、何か解決の取っ掛かりがないかということを探索し、まだ多くの現代の人々が気づいていないけれども、文化芸術には現代の問題に取り組むに当たって素晴らしい力がある、それを是非生かしていきたい、そういう流れでお話をしたいと思います。
まずは、これは皆さんが感じられていることでもあり、釈迦に説法でしょう。社会においては、文化芸術の力が、十分に認知されていません。したがって、今文明の中心になっている経済において、文化は中心に置かれていない、その結果、文化が持っている本来の力が発揮できていません。では、どうしたら良いのでしょうか。
私は、文化庁長官を三年間やっていました。その時も、そして今もですが、文化庁予算というのは、1,000億を少し超えたところでほとんど横ばいになっています。財務省に行き、文化は大事です、文化の予算は今のままではとても足りません、フランスに比べれば文化の予算は政府の支出に対する比率は10分の1です、そう言ってもっと増やすように働きかけると、財務省の方たちは「確かに文化は大事です。では、もしいま文化予算を100億円増やしたとしたら、来年どんないいことがありますか。GDPを押し上げる効果がありますか。人々が幸せになりますか、そしてそれは数字になりますか」と言われる。そもそも文化芸術の効用というのは数字になりにくいものです。そして、効果が現れるとしても10年、20年先で、しかも、因果関係が見えにくい。具体的にこの予算をつけたからこれが出来たということは明示できない、と言わざるを得ない。議論上での弱さが文化芸術にはあります。

文化芸術と経済、それぞれ大事な人間の活動分野。それぞれの本質はどこにあるのか、どこは変えてもいいし、どこは変えてはいけないのかを考える必要がある。
そこで、色々と考え「文化のもつ7つの力」というものをつくりました。1つめは、感動や悩み、祈り、感謝の念を表現して、共有すること。そして2つめは、生きる力と幸福を与えること。そして3つめは、文化自体がコミュニケーションのツールになることです。文化を通じたコミュニケーションがとれるということです。4つめは、もちろん経済効果があること。観光がその典型です。当時は、クールジャパンというアピールが始まった頃でした。5つめは、ナショナルブランドとして、あるいはソフトパワーとして外交のツールになることです。6つめは、人間はどうしてもうまくいくと固定観念にとらわれてしまいますので、それに対して文化芸術は、そういった殻を破ることにも役立ちます。これは企業のイノベーションにもつながるということです。最後の7つめは、日本人がずっと長い間育んできた、知恵や思想、価値観です。そういったものが、伝統文化、伝統工芸といった、有形無形の文化財が体現しています。我々はそれらの文化を通じ、思想や価値観を短期間で吸収することが出来る。文化財はいわば、先人たちが残してくれた宝の箱です。当時は、そういったことを並べ説得を試みましたが、なかなか予算を2倍にする、というところには至りませんでした。ですが、最近、また新しい文化芸術についての発想が出てきていますので、それをゆっくりとご紹介していきたいと思います。
なお、今日のお話は「これをやれば良い」という明確な答えがあるわけではありません。あればとっくにそれを実行しています。しかし、そういうことを目指している泉志谷君や、CILの皆さんが、答えに向かう道筋の中で、何か材料になるものが提供できればという気持ちで、今日は材料を提供します。最後の料理は皆さんがつくってください。
まず、そういう「解」を見つけるためには、文化芸術と経済、それぞれ大事な人間の活動分野ですけれども、それぞれの本質はどこにあるのか、どこは変えてもいいし、どこは変えてはいけないのか、ということをまずはしっかりと考えなければいけません。単に文化芸術と経済の融合といって、ごちゃ混ぜにしても意味がないと思います。昨日たまたまある講演を聞いていて、ラインホールド・ニーバーというアメリカの宗教学者の言ったことを聞き、紹介しようと思ってここに引用しました。全く同じことですね。
『神よ、変えることの出来ない事柄については、それをそのまま受け入れる平静さを、変えることの出来る事柄については、それを変える勇気を、そしてこの二つの違いを見定める叡智を、私にお与えください』(ラインホールド・ニーバー)
特に、最後の『二つの違いを見定める叡智』それはどうしたら得られるのでしょうか。もしかしたら永遠の課題かもしれませんが、そういった問題意識を持つことが大切です。そのためには、目の前のことだけではなく、人間とはそもそも何なのか、どういう歴史を歩んで来たのか、経済を生んだ文明とはそもそも何なのかということを、巨視的、歴史的に、見なければなりません。同時に、その流れの中で、今ここにいる自分はなにを基準にその問題に立ち向かうのかという、自己の、拠って立つ基盤を持って頂かなければいけないだろうと思っています。
大局観とは、時間、空間、分野を越えて事象を俯瞰するということです。生命や人類について、専門の枠を越えて全体を考えていくということがまず必要です。それによって、現代を分析して未来を自分でつくっていくということです。
座標軸というのは、こうした流れを見据え、自分を位置づける、設定するものだと言えます。大きな流れ、例えば鳴門の渦潮のようなものに巻き込まれているだけでは、課題を解決することは出来ません。今自分はどちらを向いているのか、常に、どちらが陸なのかを把握し、いかにうまく立ち回れるか、ということを考えることが大切です。そういう行動指針を持たなければいけないという、お話をしたいと思います。
大局観と座標軸の双方を持つと、どういう良いことがあるかと言いますと、固定観念を取り払うことができる力になります。人間は一度成功すると、そのやり方で良いと考え、固定観念が生まれてしまいます。そうすると、変えても良いもの、変えてはならないものの判断を誤ってしまうことがあります。そこで、大局観を持ち、大きな流れの中で、何を変えたほうが良いのか、悪いのかの判断がつくようにする必要があります。

ここにいくつかの固定観念になり得るものを紹介しましょう。まず、未来は、過去から現在までの流れの延長であるという考え方。人類には普遍的な価値というものがあるという考え方、欧米風の普遍主義ですね。社会は、普遍的な善という目標にむかって進歩する考え方、これを進歩史観と言い、西洋、キリスト教社会に根付く発想ですね。それから資本主義というものは、経済は成長を続けることで豊かさが増し、進歩をしていく、将来の目標に不可欠な力を持っているのだという考え方です。企業で言えば、自由競争の下で最大利益を目指すことが進歩に役立つという、アダム・スミスのような考え方もあります。そして、西欧中心史観、西欧の文明は、人類が収斂していくゴールだという考え方。それから、科学技術は万能であるという考え方、科学技術はどんな問題であれいずれ解決してくれる、だから科学技術をしっかりとやっていれば良いのだということです。そういったことに対して、当たり前だと思うところもあると思いますが、本当にそうだろうか、と考え直していくことが必要なのではないかと思います。
では、これから大局観の例をご紹介したいと思います。ここでは、宇宙と地球の歴史、特に生命とは何なのかということについて振り返りたいと思います。次に人間とは何か、人間が作り始めた文明というものはそもそも何なのか、ということをお話していきます。

あらゆる秩序は必ず崩れる、乱雑になっていく、もとには戻らない。
これが地球ですね、美しい星です。138億年前に宇宙が出来、「ビッグバン」というものがおきました。46億年前に地球が生まれ、38億年前に生命というものが誕生した。この生命というものは、まだほとんどわかってはいませんけれども、知れば知るほど不思議なものです。特に生態系、最近言われ始めている「動的平衡」、そして日本人の大隅良典先生という方が発見しノーベル賞をとられた「オートファジー」細胞の自食作用……そういった様々な作用が合わさって、生命というものが38億年間この地球上で生きてきたということですね。
順番に言うと、まずはビッグバンです。宇宙は高温高密度の状態から始まり、大きく膨張することによって、低音低密度になっていく。これが無限に続いていくわけです。そこで生まれたのが、エントロピー増大の法則というものです。聞かれたことがあると思いますが、あらゆる秩序は必ず崩れる、乱雑になっていく、もとには戻らないという大原則ですね。例えば、お湯と水を混ぜるとぬるま湯になります。しかし、それがまたお湯と水に戻ることはない。海岸で砂山をつくっても次第に崩れていって元には戻らない。宇宙はそういった大きな法則に支配されている。これには誰も抵抗できません。
他方、生命というのは、そういった物理現象の中で、色々と工夫をして、38億年間つないできたわけです。具体的には、無機物を植物が太陽光を使った光合成によって、有機物と化学エネルギーに換え、酸素を出すという大変重要な役割を果たしていく。タンパク質やエネルギーを草食動物が食べ、それを肉食動物が食べ、そして、そのタンパク質が次々に移動をして、最後排泄物や遺体となって、地面に戻っていく。その有機物を無機物に変えるのが微生物ですね。そうして、無機物はまた地中にもどって、再び植物による光合成の生産要素となる。化学エネルギーも同様です。

「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。よどみに浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとゞまりたるためしなし。」ということであり、生命体とは一瞬の淀みであり、実態のある個体ではない。
漫画をつくってみました。ここに無機物があります。例えば炭素。それを植物がCO2と太陽の光エネルギーとを一緒にし、光合成を行い、有機物タンパク質、化学エネルギーをつくり、酸素を出しますね。そして、草食動物は酸素を吸い、タンパク質を食べ、化学エネルギーを吸収して、子供をつくる。ライオンが来たらもちろん逃げます。その時化学エネルギーを発散する。ライオンは肉食動物ですから草食動物のシマウマを食べる。食べることでタンパク質と化学エネルギーを得て、もちろん酸素も吸い、それによって子孫を残します。そして死んでしまうと、今度はそれを細菌が分解して、無機物になる。そういうことで、同じ量の無機物が、ぐるぐると循環することによって、生命が維持されています。大変不思議なメカニズムですよね。
もう一つ面白いのが動的平衡というものですね。先程エントロピーの増大という話をしました。エントロピーのルールのもとでは、物事はどんどん崩れ、もとに戻りません。我々は老廃物を出します。時が経ち、歳をとれば高分子は酸化する。タンパク質が変性する。油断していると、すぐに秩序は崩壊してしまいます。それはすなわち、生命体の死を意味しますが、それに抵抗するために、常に自分を壊し、新しくしていかなければなりません。自分自身をフレッシュに保つために、エントロピーが低い状態をできるだけ伸ばしていく。エントロピーが高まってしまったら排泄物としてどんどんと外に出す。そして新しい食事や酸素によって、低いエントロピーの状態を維持していく。そういったことも個体は永久に出来るわけではなく、最後は死んでしまうわけですが、自分が死んだとしてもその間に子孫を残すので、種というのは保存されます。個体は死んでしまい、エントロピーに負けるけれど、種としはエントロピーに抵抗して生命を持ち続けるということです。神様が作られたのかどうか知りませんが、大変に素晴らしい仕組みです。
とても簡単に言うとこういうことです。毎日食事によって、タンパク質など、新しいものを取り入れます。それは身体の中にたまりますが、いつまでも溜めてはおけない。古くなったものはどんどん捨てる必要があります。つまり、排泄物として、汗として。皮膚が剥がれてどんどん落ちていくのもそうですね。そうすることによって、個体というのは、固定しているのではなく、常に流れていると言えます。常に新しいものが入り、古いものが出ていっている。つまり「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。よどみに浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとゞまりたるためしなし。」ということであり、生命体とは一瞬の淀みであり、実態のある個体ではない。流れの中の一時的なたまり場だと言うわけです。そういうことによって、生命は個体を維持しているという、不思議なことです。
もう一つはオートファジー、つまり自食作用というものです。こちらも非常に面白いものでして、簡単に言えば、生命体の細胞は、細胞の中にある自身の細胞質成分というものを食べて分解して、アミノ酸を得る、というものです。

新たな環境に適するものが残る。それはいわば進化であり、生命の継続。
これは細胞ですね。液胞と細胞質成分というものがあります。しかし、最近までなぜ液胞があるのか、細胞質成分がなぜあるのかわかりませんでした。細胞にとって必ずしも必要なものではないらしいんです。ところが大隅先生が発見したのは、この液胞が、細胞質を食べるということでした。自分のタンパク質を食べ、アミノ酸に分解する。古くなってエントロピーが高まった細胞のタンパク質は、自分で食べ、エントロピーの低いものにして、もう一回使うということですね。誰が考えたかわかりませんが、そこまでして、生命は自分を維持してきたということです。
今申し上げた動的平衡、つまり個体とは一時的なとどまりにすぎないということと、古くなったものは捨てるだけじゃない、自分で食べて新しくする、そういう素晴らしい作用によって、エントロピーの増大に抵抗し、個体、そして種の生命を、維持してきたということですね。それから、生態系という食物連鎖、シマウマをライオンが食べる云々、そうすることによって有限の物質が、無限に循環をして生命を維持しています。この食物連鎖というのは大変重要です。
更にその循環の担い手が絶えないようにする必要性があります。色々な環境変化が起こるわけですから、単純なサイクルの方式では、種が駄目になってしまうかもしれない。そこで、多様性が大切になってきます。いろんな種類の動物、植物、昆虫、細菌がいるからこそ、環境変化でどれかが駄目になったとしても、他の種が生き抜いてくれるわけです。それは個体においてもそうだし、動物としてもそうです。数限りなく違うものがある、おまけに、突然変異で変わったりもする。それによって、新たな環境に適するものが生き残っていきます。それはいわば進化であり、生命の継続ですね。
コロナウイルスも同様です。どんどん変異種が出てきています。ワクチンが出来ても、治療薬ができても、それをかいくぐっていけるものが繁殖していく。つまり、ウイルスの多様性があるからこそ、しぶとく、我々を苦しめていると言えます。
そういった、人間がなかなか考えつかないようなメカニズムで、38億年間バランスを維持してきたのです。例えば、ライオンがシマウマを食べ尽くしてしまうと、餌がなくなって自分が滅んでしまいますね。だから、ライオンは、シマウマを食べ尽くさない程度に食べる分を調節しています。シマウマも同様に、草を食べ尽くすと生きていけなくなるので、草が元に戻ってくれるぐらいの量に留めている。ライオンも、シマウマも、植物も、捕食者と被食者の関係にあるけれども、そういった調整することで、バランスや生態系の循環を保ってきています。考えてそうしているというよりは、人口調整ができる種族が残ってきたのかもしれませんね。
今日は、ドイツの方もいらっしゃいますね。『ハーメルンの笛吹』という小説があります。その元となったのが、レミングとかいうネズミです。何年か一度に大繁殖をする。そうすると不思議なことに、突然集団で海に向かって突進して、沢山のネズミが集団自殺をすると言われています。それによって人口調整をしているのです。だから、ネズミの餌はなくならない。ネズミを食べる猫たちのバランスもとれているということです。これは単なる言い伝えで科学的に証明されていないそうですが、そういう話があるということだけ申し上げておきます。いずれにしても、そのような知恵が、色んなところにある……知恵といっていいのかわかりませんが、我々からみえれば知恵のようなものがあるからこそ生命は保たれてきた。そのことを、我々は社会を運営するときに、しっかりと理解しておかなければいけない。ということです。
ところが、人間が文明を発達させることによって、この素晴らしいバランスのとれた自然を、どんどん壊してしいました。例えば、森林破壊。エネルギーをとるためにどんどん木を切って燃やしました。そして、居住地をつくるために、平野をつくるために、畑をつくるために森林を破壊した。その結果、植物の数が減れば光合成ができない、CO2が吸収できなくなるから温暖化になる。野生動物が追い出されて絶滅をする。そうなればさきほどの物質循環、食物連鎖というものに影響を与えるし、野生動物は畑とか人里に出てきて感染症を拡大してしまうことに繋がります。
それから、農業革命が起こりました。人工的な食糧増産によって、人口が急激に増大した。ライオンは増大しすぎたら、シマウマを食べ尽くして、自分も駄目になります。しかし、人間は食糧を増産したため、人口が増えても一応は生きていける。それによって、みるみる人口が増え、都市化が進み、更には、自分が美味しいと思う野生動物を捕まえ、家畜にしました。したがって、そうでない野生動物はどんどん滅びていくことになりました。家畜になりそこなった狼も絶滅してしまいましたね。今、地球上にいる哺乳類の9割以上が家畜だそうです。食物連鎖や多様性に大変なダメージを起こすとともに、家畜から感染症も広がります。家畜自身も「三密」の中でインフルエンザに襲われ、「殺処分」にされます。
そして、技術革新により、大量生産、大量消費が始まりました。プラスチックは、分解して土に戻すことが出来ない、つまり物質循環を妨げてしまいます。人間はそういったことを、どんどんやってしまっています。最近はやっと反プラスチック、反ビニール運動が始まりましたが、とても追いつかないほどの大量廃棄が行われています。エネルギーの大量消費も問題です。石炭、石油を大量に燃やし、CO2が出て、温暖化になる。人間は、本当にろくなことをしてない、そう言わざるを得ません。

制度は完璧で美しい。しかし、それを運用する人間が不完全。
これが先程の循環ですが、ここに人間が出てきました。何をしたかというと、森林破壊、農業・牧畜革命、大量工業生産、エネルギー消費……したがって、光合成もCO2の吸収も、酸素を出すのも、そして物質循環や食物連鎖もその機能が低下し、野生動物も、どんどん滅びてしまいます。あげくの果てに、地中にある炭素を、石油を燃やすことによって外に出し、それが、空にいって、温暖化になってしまいます。家畜も増えて、感染症の媒体に。本当にまぁひどいことを、人類はやってきたと言わざるを得ないですね。もちろん、それらは、事前にわからなかったわけではありません。ここにあるような有名な書物は警告を発してきました。例えば、レイチェル・カーソン『沈黙の春』やローマクラブ『成長の限界』、ヨハン・ロックストローム等の『プラネタリーバウンダリー』です。さらに、多様性に関する条約、京都議定書、MDGs、最近のSDGs、等々ですね。そういった、何とかしようという動きはあったけれども、自然破壊は止まっていません。
それはなぜか。やはり最後は、経済成長しなければならないとの思い込みがあるからです。成長しなければ、進歩主義や普遍主義という理念を実現できない。脱成長なんてありえないという思い込みがあります。同様に、科学技術はいずれ問題を解決してくれる。気候変動も、感染症も、最後は科学がやっつけてくれるという希望的な観測もあるでしょう。
最近、環境問題についての意識が高まり、科学技術を用いて何かしなければならないという流れが始まりました。しかし本格的な解決策ではなく、わかりやすく、かつ経済のシステムにうまく乗ることだけやるという傾向があるように思います。最近の脱炭素のブームはその一例です。脱炭素をやらない企業はもう生きていけないと言いますが、本当に脱炭素だけでいいのだろうかと考える必要があります。例えば、ガソリン車をやめ、EVに変えるということ。あたかもそれで全てが解決するように思われていますが、実はEVをつくるには、たくさんの銅が必要です。それからリチウム電池。リチウムは希少資源です。リチウムは、中国等、ごく一部にしかありません。そうすると、そういった必要資源を確保するために、開発途上国での児童労働などが発生してしまうことがあります。銅はアフリカ、コンゴ等にありますが、そこでまた先進国の企業が行って、銅が必要だと言って、低賃金で働かせてしまう。それによって、貧困が続くし、むしろ先進国による収奪は増してしまいます。更に、銅からEVをつくるにあたっては、工場で大変な量の二酸化炭素を出してしまいます。そういったことは計算されず、ガソリン車が出す排気ガスだけを計算して、それがなくなれば良いと考えられています。
一見良いように見えて、実はEVをつくる過程でたくさんCO2を出してしまいます。加えて、実際は途上国に負担がかかりや森林も破壊することに繋がる。そういうことに目をつぶって、脱炭素ですべて解決する、形だけやっているという競争になってしまった。結局は、その場しのぎで終わってしまうのではないかと危惧しています。金融危機も似たようなものですし、戦争もやめようと何度言われたかわかりません。いろいろな制度はつくりました。しかし全然終わっていませんね。これは結局人間の浅はかさであると言わざるを得ません。わかってはいるけれども、根本的には何も出来ていない。
では、何故そのようなことになってしまうのか。その一番奥にあるのは欲望です。オリンピックの標語にもありますが「より速く、より高く、より強く」これは良い言葉でしょうが、例えば、100万円貯まったけれど、一部の人間はそれで満足しなくなっていますね。じゃあ、これを投資して200万にしよう、500万にしようと考えます。新幹線、すごく速い、けれども、リニアはもっと速いよ、ということも同じです。満足しない。先程、ライオンの話をしましたが、ライオンっていうのはお腹がいっぱいのときは、シマウマがそばを通っても見向きもしません。お腹が減ってくるとシマウマを襲って食べます。人間はどうでしょう。お腹がいっぱいのときにおいしいものが出てきたら見向きもしないでしょうか。人間は食べられなくともとりあえずとっておき、冷凍保存するということが出来ますね。そうすることにより「足るを知る」ということを人間はどんどんと忘れ、よりおいしいものをよりたくさん求め、将来のためにそれを貯める、そういう風になってきています。
欲望については、ライオンのほうが遥かに人間よりえらいですね。ちゃんと、足るを知る。自分が生きていく、子孫を残していけばそれで良い、それ以上のものは望まない。しかし、人間はそれ以上を望んでしまいます。それ以上を望んで、それが実現する技術がなまじあるから、ますますそうなりますね。
欲望に加えてもう一つ、人間の性は、思い上がりです。科学技術があれば何でも解決できると考えてしまいます。人間は、せっかく、経済や資本主義経済という素晴らしい文明、科学技術を培ってきました。民主主義もそうだし、資本主義もそうですが、文明というものは制度であり、しかも、とても立派です。完璧で美しい。しかし、それを運用する人間が不完全ということですね。車と似たところがあって、ベンツであれ、レクサスであれ、その技術は素晴らしいし、事故が起きないように精密設計されて作られています。しかし、そのメカを知らず、酔っ払って運転すれば、それは事故を起こしてしまいますね。文明という素晴らしいシステムをつくったはいいけど、ちゃんとそれを運用できてない。人間というのは不完全であり、そういう浅はかさがあるんだということです。以上が、自然における生命、生態系の発達とそれに対する人間の負の行為の概観です。

宇宙に出てふっと地球の方を振り返り、はっと気がつくことがある。地球には国境はない。
もうひとつ、人間自身の社会の話をしてみましょう。人間、つまりホモサピエンスが生まれたのが20万年前だと言われていますね。大元はおそらく700万年前くらいに、アフリカのエチオピア南部に生まれたようで、そこで発見された女性の人骨(たしかルーシーと名付けられた)が人類共通のお母さんだと言われていますね。アフリカに生まれた類人猿が、だんだん世界中に広がっていったと言われています。北京原人やジャワ原人もいましたが、そういう原人はみんな滅び、最終的にはアフリカの類人猿が世界に広がって、やがてホモサピエンスになったというのが今の定説のようです。その間に道具を使うことを覚え、火を覚え、先に言ったような、認知革命、農業革命、産業革命、科学技術革命、情報革命と、もう加速度的に数百年の間にものすごい進歩を遂げてきました。
認知能力というのは、知覚、思考、言語能力などのことで、これによって、自然の中にあるルールを見つけ出しました。万有引力の法則とか、そういったものの発見です。同時に、それから抽象的な概念をつくり出しました。真理というもの、秩序とか市場とか正義とかで、こういうものは自然界に物理的には存在しません。これらは、人間が勝手に考えだし、言語化したものですね。それをさらに人間の活動に当てはめて人文科学、社会科学、哲学、文学、政治学、経済学として発達させた。これは『サピエンス全史』を書いた、ユヴァル・ノア・ハラリの言葉ですが、彼はこれらのことを「虚構」であり「共同幻想」だと言っています。このように抽象理念を制度化して、国家というものをつくり、マーケットというものをつくった。そして、権力機構や法律をつくり、統治をする。国境をつくる。更に、それらの最も素晴らしい運営方法は、民主主義だということを考えだした。経済面でも、ものを生産するだけではなく、交換することで新しい価値が生まれる、より価値が高いところに持っていき、高く売れば利益が生まれる。その利益でまた新しいものをつくり、それを作れないところに輸出することで金を儲ける。そういった交換経済、それを司る貨幣、そのお金を供給する金融。資本主義の中で、そういうものを人間が考え出してきました。このように、理念をつくり、それを制度化し、機械をつくったり、交通手段として電車をつくったり、物理的な手段をつくり、増やし、発展させることで、大変な繁栄をつくってきたということです。そして、それらはもちろん、自然を破壊したわけですね。

もし小学生に世界地図を書いてごらんと言えば、おそらくこういう地図を書くと思います。日本がここにあって、ここに中国があって、ここにロシアがあって、アメリカがここだ。だけどこれはほんとの地球の姿でしょうか。宇宙飛行士の話からよく聞きますが、宇宙に出てふっと地球の方を振り返り、はっと気がつくことがある。地球には国境はないのだと。

人間が素晴らしい文明をつくったのに、それを十分に乗りこなせてい�ないということですね。
地球というものは、実際はこういうものであって、国境は無い。共産主義国を赤で塗ることも、アメリカの中で民主党と共和党を赤とブルーで染め分けるとか、そんなことは人間の上面の作業に過ぎないのだということを改めて感じた、ということですね。
そして、人間はこれだけ素晴らしい制度をつくってきましたが、決して人間の社会というのは、平和ではありません。幾度も戦争し、どれだけの人を殺してきたかわかりません。それ以外にも、金融危機や、テロもあれば、無差別殺人もあります。温暖化を招き、感染症を招いて、貧富の差や飢餓も存在します。人間全体は豊かになっているはずなのに、富の偏在で貧困があります。その結果として、移民や難民が増える。それをきっかけとして、ヨーロッパなどで、極右ポピュリストが生まれる。そういう状況では、民主主義はちゃんと機能しない。それをいいことに、中国やロシアは民主主義など綺麗事に過ぎないと言い、独裁的な体制を維持するばかりか、途上国を反民主主義陣営に取り込もうとしています。英国のEU離脱もヨーロッパの理念に反発をしての結果ですね。アメリカのトランプ氏の大統領選出をきっかけとする、一連の出来事もそうです。つまり、民主主義とか資本主義とか、格好の良いことを言っているけど、結局はエリートだけが得しているのでないか、と。例えば、白人の中間層ですら、自分たちは置いてきぼりにされた、もうこんなシステムどうでもいい、明日食えるようにしてくれる人がほしいという思いがあったということです。こうした色々な問題を抱えている実情を見ると、到底文明は素晴らしいなどとは手放しには言えません。差別、憎悪、不満、対立、分断、そういうものがどんどんと表に出て、コロナによって先鋭化しています。人類は、数百年の文明の進化で、著しい進歩したと考えてきましたが、やはりどこかおかしいのではないかと思わざるを得ません。
先ほど言ったように、この文明の中心をなす制度が悪いわけではありません。制度はベンツなどと同じように、ほぼ完璧な構造です。しかし、実際のマネジメントが追いついていないということです。理念は素晴らしい。合理主義に基づく資本主義、アダム・スミスも、理念体系としては正しいことを言っています。しかし、人間というものは経済学が想定しているように、常に合理的に行動するわけではありません。欲望があり、利己主義であり、妬みがあり、差別や分断の感情を持っている。そういう人間の欠点を無視し、いつかなおる、誰かがなおしてくれる、近代人ならなおせて当然だということで、ずっと引っ張ってきてしまいました。しかし、結果として、この問題はそう簡単に解決はしませんでした。結局一部のエリートや大企業、政治家が、その制度を自分の利益のために使ってしまい、庶民にまで届かないということが起きました。そのような背景から今、庶民が猛反発をしているということです。
それどころか、制度、つまり民主主義なんていうのも“まやかし”じゃないかとさえ言われてきています。たしかに、理念と現実は違うということはみんなが知っていることですが、現実に合わせ、理念を修正するということはしてきませんでした。なぜなら、こんな素晴らしい理念体系は壊したくないからです。むしろ、強引に現実を理念に合わせようとしているのではないでしょうか。選挙が大事だ、民主主義が大事だ、そうすればいいんだと言い、例えば、アメリカやイギリスは、途上国に英米式の民主主義を押し付けてきました。これが理念で、これをやれば幸せになる、安定するんだと言い、押し付けた。地域によって、文化によって、多様で治め方も違うはずなのに、それらを無視して押し付けた結果、途上国が反発した。それが、欧米の圧倒的力の下で一時的にはうまくいってしまったことから、為政者、理論家は傲慢になってしまいました。何か問題が起きてもそれは科学技術が進歩するのだから必ず解決できるといって真剣に取り組みませんでした。そして、結局はエリートが利益を得るという、悪徳と言われても仕方ない、ぎりぎりのところまでやってしまっていることもあります。
アメリカのアカロフとシラーという、二人のノーベル経済学賞の学者が書いている『不道徳な見えざる手』という本があります。そこに詳しく書いてありますが、アダム・スミスの「見えざる手」というものは現実では理念の通りに機能しない。何故なら現実社会では情報が非対称的で、売り手の人間がみんなずる賢いから、法律にふれないギリギリのことをやって、情報を全体に与えずに自分たちだけが利益を得られる構造になっています。結局、欲望というものは、果てしなく広がり、それを誰もコントロールできなくなってしまっているということです。せっかく人間が素晴らしい文明をつくったのに、車で言うとメルセデス・ベンツをつくったのに、それを十分に乗りこなせていないということですね。

物質的な価値に直結するようなデータや知識の量は評価する。心の豊かさ、共感、協調性など、質的な価値が軽視されてしまっています。
もうひとつ、これは、今日の会に一番関係することです。文明が発達したことによって、文化の価値が相対的に軽視されていると言わざるを得ないということです。経済の仕組みとは、生産によって新しい価値を生み、それによって得られる利益を更なる生産と価値創造に向けることで富を永遠に増やしていくというもので、そこでは、合理性、効率性、生産性、そして物質的な、数字ではかれる価値というものを基準にしています。この仕組はその限りにおいてちゃんとまわり、これだけの経済成長が実現しました。政治の方は、統治することが目的ですから、法律をつくります。それと同時に、民衆が反発しないようにそれらが公平であることが必要で、そのためには何をするにも公益性、つまりみんなのためになることを行う必要があります。それが政治の仕組みですね。これに対し文化というのは生きること。生きがいを感じることが目的だから、感情とか情動とか感動が大事です。感動しなければ、文化というのはほとんど存在しない。だから、合理的だったり、効率的だったり、生産性を重んじたり、物質的な価値に引っ張られたり、公平性や公益性ばっかり気にしていたら、ろくな文化は出来ません。文化の拠って立つ基盤は、政治や経済の基準と合わない。つまり、今は特に経済が主流ですから、経済の土俵にはなかなか乗れないわけですよね。だからこそ、文化芸術や人文学は軽視されて、予算もなかなかまわってこなくなります。
それでも、文化は大事だと言う人はいますから、この現状を何とかしようとする試みはいくつも起きています。例えば、政治経済のメカニズムの中でも、なんとか文化を応援する仕組みをつくろうとしたら、政治や経済が納得するような文化活動をして初めて予算がもらえる、と言うことになります。そこの中継ぎを考えたのが、イギリス発祥のアーツカウンシルです。今、日本でもアーツカウンシルブームで、文化庁はもちろん、10を超える自治体が、その地域のアーツカウンシルをつくっています。そこでは、財政が厳しい中で、どうやったらより効率的に目的が果たせるかということを考えます。ただ、役人が鉛筆をなめて何かを企画しても、アーティストはついて来ません。アーティストの言うとおりにだけやっていたら、本当に社会にとって有意義な活動になるかどうかわからない。役人とアーティストの仲立がいるだろう、ということで、政策の目的や、どういうルールが必要なのかを知りながら、同時に文化芸術の現場を知っているという組織です。どうすれば水と油の政治と文化の間で文化芸術活動が活発化するかがわかる、双方の領域がわかるつなぎ役として、プログラムディレクター(PD)、プログラムオフィサー(PO)という役職をつくり、なんとか仲立をしようとする活動です。
さきほど、文明が発達したことで、文化が蔑ろにされたと言いましたが、もうひとつ、人間の生き方、生き様に対しても、マイナスな影響があるんじゃないかと最近思うようになりました。今の、情報化とか利便性がどんどん進むことが大事だという社会にあっては、どうやって生きるか、どうやって意味ある生涯をおくるかということよりも、どうやって良い点をとるか、どうやって利益をあげるか、どうやって出世するかが優先されてしまいます。つまり、教養や人文知の価値がどんどん下がっていくわけです。それらを誰も評価しなくなってしまう。最近、大学の人文社会系の学部に予算が回らなくなり大変だと聞きますが、文化芸術もそうですね。残念ながら、現代とはそういう状況になってしまっているということです。結局、物質的な価値に直結するようなデータや知識の量は評価する。心の豊かさ、共感、協調性など、質的な価値が軽視されてしまっています。
教育においても同様です。認知能力である、算数・数学とか論理性、テクノロジーを重んじる。しかし、非認知能力、つまり、芸術、文化、遊び、そういったものがどんどんと軽視されています。 そうなると、常に数字にあらわれることを重視し、競争で勝てるかどうか、つまり、友達を見るとそいつは敵か味方か、ライバルかパートナーか、という二分法になってしまいます。それによって、争いが生まれ、うつ病が生まれ、引きこもり、いじめ、虐待、自殺など、最近の社会問題がどんどん増えてしまう。やはり、この文明の一方的な価値判断基準が、人生のすべてに広まってしまっているが故に、人間関係がどんどん荒んでしまっていると言わざるを得ないのではないでしょうか。そういったことを、色んなかたちで、様々な人が書いています。

人類は文明の力で繁栄を遂げた。しかし、大変な負の側面がある。
この新井紀子さんの本が有名ですね。最近の高校生のことでしたでしょうか、文章が読めない、AIと同じようなことしかできない、ということを仰っていました。もうひとつ、今日は小説家の方もいらっしゃると聞いています。阿刀田高さんの『あらすじ』という非常に短い短編があります。主人公が区立の図書館に行って開館を待っていると、隣にガリ勉風の学生が一生懸命勉強している。そこで「毎週日曜日にくるの?」と聞くと「来ます」と学生は答える。手にたくさん学習参考書を持っている。そして「ここで受験勉強をするんです、家が狭いから」なんてことを言う。主人公は、昔は図書館っていうのは教科書なんか持ち込むところじゃなくて、小説を読みたくて来たんだけどれもなあ、と思います。そこで「小説は読まないの?」と聞いてみると「小説は知っているけれど読みません」って答えるんですね。「どういうこと?」と問いかけ、例えば「芥川とか夏目漱石とかは知っている?」と水を向けてみると「ああ知っています、夏目漱石は明治の文筆家で、坊っちゃんが初期の作品で、こころが最後の作品です。で、坊っちゃんはこうこうこういう話で、こういう小説史上の意義があります。芥川龍之介の作品にはこういう意義があって、芸術至上主義というものがそこにあらわれています」と、すらすらと答える。主人公は「え、読まないでどうして知っているの?」と聞くと「塾で習いました」と言うわけです。主人公が「塾で習ったってちゃんと読まなきゃ意味ないのではないの」と言うと「いえ、読む必要はありません、小説なんか読んだって意味ありません。あらすじさえわかっていれば受験には受かるんです、試験問題には正解はできるんです」と平然と答える。「どうしてそんなことやるの?」と聞くと「いや、そうやって東大にいって、大蔵省に入って、最後は良い天下りをする、それが良いんです」と堂々と言う。ということで、その主人公は「そこまで自分の人生わかっているんだったら、もう生きる必要ないでしょう」と考える、という話ですね。要するに、小説を読むということは、主人公の生き様や悩みを自分が共有して、あたかも自分がその主人公であるかのようにして答えのない問題に取り組むことができるということです。それが生きることに繋がっているということです。データで全部処理してしまったら、それは生きることにはならない。そんな人生、生きていても意味がないのではないかという問いかけですね。
それから芸術、文化、遊びといった非認知能力、これが大事だということは、OECDが出しているレポートや、ジェームズ・ヘックマンというアメリカのノーベル経済学者が書いた『幼児教育の経済学』という本でも言われています。この本で言っていることは、小学校に入る前くらいの幼児に、非認知能力中心と認知能力中心と、教育の仕方をふたつにわけて、40年間フォローした結果です。つまり、ひとつのグループには認知的な能力、算数や論理を教える。もうひとつのグループには、それも教えるけども、むしろ遊ばせたりゲームをさせたり、音楽を習わせてやったり、演劇をやらせたりする。そうして40年間データをたくさん集め、結論づけたことがこの本の凄いところです。結果、小学校に入るくらいまでに、非認知能力を高めた子どものほうが、勉強も出来、良い学校に行き、最後に生活支援を受ける比率も少ないということがわかりました。つまり、非認知能力の教育を早いうちに受けたグループの方が、認知能力のみの教育を受けたグループよりも人生が豊かに成功し、経済的にも独立した生活をした、ということです。
ですから、これはもうぜひ、子供を持つ方々や、教育熱心な皆さんに言いたいことですが、小学校の間くらいは、塾にやって算数や英語をやらせるだけではなく、芸術をやらせなさいということです。芸術を学ぶということは、学校の中だけではなかなか無理があります。芸術をお稽古として始める。音楽でも絵でも、演劇でも良いです。それを日常の中でやることで、子供のモチベーションが上がり、困難を克服する力が上がり、良い友達と協調し、何かを成し遂げる力がつきます。そうなれば、クラスで習った認知能力も、吸収がしやすくなる。だから算数の点数も、むしろ良くなる。そういうことをぜひ、子供を持つ方々に伝えたい。もちろん、本当であれば、学校でやるべきです。今音楽の時間や図工の時間がどんどん減っているようで、とんでもない話ですね。目の前の認知能力、ITがこなせるかどうか、算数ができるかどうかで、人間を判断している今の教育は大きな間違いだと言わざるを得ません。非認知能力の重要性を、国際経済機関であるOECDですら言っているわけですから。
私が言いたいことは、人類は文明の力で繁栄を遂げた。しかし、大変な負の側面がある。自然を破壊し続けたことで、とんでもないことになってしまうのではないかということです。人類社会の秩序の維持も成功はしておらず、民主主義も崩れ、資本主義も崩壊するかもしれません。また大きな戦争が起こるかもしれない。核戦争、サイバー戦争で自滅してしまうかもしれない、もう、そういうところまできています。個人の心の平和、社会の安定も損なわれている。生きているということの意味を人々から奪ってしまっている。そしてその深刻さは、もう限界に近づいているのではないでしょうか。気候変動だってあと1度か2度あがれば、大変なことになってしまいます。感染症も、これからより強いのが生まれてくるでしょう。なにかのボタンの掛け違いで、大きな戦争も起きてしまうかもしれない。テロもますます高度化している。サイバー攻撃の脅威もあり、目に見えないだけに怖いものですね。社会にはうつ病、自殺、現代病も増えている。表面的な繁栄の内側には、そういったものがあるということです。
では、どうしてそれらを放置してきたのでしょうか。それは、繰り返しになりますが、欲望と思い上がりから脱しきれていない、人間の弱さよるところでしょう。そして、AIはこうした問題を解析することはできません。
長い歴史の中で、文明を過信した人間の思い上がりへの、反省はなかったのかと言うと、実は、色々とありました。「人文知」即ち一般教養の中には、過去の歴史、文学、哲学、芸能、伝説など、いろいろな教訓が含まれています。まずはその具体例をお話しします。人間が思い上がるとえらいことになる、という話です。

まずは、皆さんも良くご存知の『ノアの方舟』。主は、人の悪が地にはびこり、そして、その心に思いはかることがいつも悪いことになっていることを心配されます。人間は本当に悪いことばっかり考えているわけです。自分の欲望を伸ばすことばかり考え、他人のことは本気で考えていない。主は、自分がそういう人をつくってしまったことを悔いて、わたしが創造した人をぬぐい去ろう、もう全滅させようと思い、大雨を降らせました。しかし、ノアというやつはいいやつだから残してやろうと。それが、伝説的には我々の祖先であって、ノアのおかげで我々は生き延び、人間は続いているということになります。しかし、今までお話ししてきたことを考えると、神様にしてみれば、ノアを救ってやったばっかりに、現代の人間どもはもっとひどいことになっている、と、散々悔いておられると思います。

もうひとつは、中国の『荘子』という紀元前の文書に出てくる『渾沌』という話しです。渾沌という怪物が海に住んでいるんですが、北の海に忽(こつ)、南の海に儵(しゅく)という名前の、やっぱり怪物がいるんですね。ある日、忽さんと儵さんは渾沌さんから接待をうけます。そこで、おおいに感激して、忽さんと儵さんは「なんとかして渾沌さんにお返しをしたいね」「どうしたら渾沌さん一番喜ぶだろう」と相談します。「そうだ、渾沌さんはああいう顔で目も鼻も口もないじゃないか」「目、鼻、口、耳をあけてあげよう」「7つの穴をあけてあげれば、きっと人間みたいにものが見られるし鼻がきくし、ものを食べられるようになるから喜ぶだろう」といって一日にひとつずつ穴をあけ始めます。7日目、ついに7つめの穴があいて、人間と同じになったと思った瞬間に、渾沌は死んでしまいます。これは人間には、自分たちは他者がみんな人間になりたいと思っているような素晴らしい存在なんだという思い上がりがあるが、実はそうではないんだよというメッセージだと思います。東においても西においても、人間は思い上がるという悪いくせがあることを、古代の人ですら知っていたということですね。

それからゲーテの『バラード』ですかね。これはディズニーの『ファンタジア』というアニメにもなったと思います。『魔法使いの弟子』です。ある魔法使いに弟子入りした若造がいて、ある日、魔法使いがちょっと用をたしてくるから、その間に夕食の準備しておいてくれ、水をくんでおいてくれと言います。弟子は「わかりました」と言って魔法使いを送り出したあと「水を汲むのは重いしなぁ。そうだ、さっき魔法習ったな。じゃあ箒に魔法をかけて水を運ばせよう」と言って、ちちんぷいぷいとやると、見事に箒は立ち上がって水を汲みはじめるんですね。そして、どんどん水を汲んで水瓶がいっぱいになり、さあもういいかなと思い、ふっと気がつくと、その魔法を止める術をまだ習っていなかったことに気が付きます。「どうしよう、もうやめろ、やめてくれ」と言っても箒は何食わぬ顔をして水を運び続ける。どんどんどんどん水は溢れ、台所からも溢れてくる。「もういいかげんやめろ」と言って、弟子は鉈で箒を真二つに割ります。そうすると、2つに割れた箒が、それぞれがまた水を運び続ける。倍の量でまた水が増えていく。弟子が溺れ死にそうになったところで、魔法使いが帰り、魔法をといてくれます。これは、ゲーテが、人間がいかに科学技術の生半可な知識に溺れ、自分の欲望を満たしたり楽をする口実のために使い、身の破滅を招くかということを当時から予言していたと思わざるを得ないような話ですね。

それから、孫悟空もそうです。お釈迦様に「俺はすごいんだ、金斗雲という雲にのれば一瞬のうちにどこまでも飛べるんだ」と言うと、お釈迦様は「ああそうか、やってみろ」とおっしゃる。悟空は「わかった!」といって金斗雲を呼び、サーっと行って何千里か先のところで、柱か何かに自分の印をつけ、また何千里と戻ってくる。で、お釈迦様に「行ってきました。行った証拠に目的地の柱に印をしてきました」というと、お釈迦様は手を開いて「これかね?」というと、その指にさっき孫悟空が書いた印がある。要するに、何千里も飛んだと思ったけど、お釈迦様の手の中を動いたにすぎなかったということです。つまり、それだけの思い上がりが、人間にはある。やはり中国の文化は良いですよね。ギリシャやローマの文明と同じような大文明をつくっています。思い上がりへの反省と警告は、洋の東西を問わず昔からあったということです。
ではそれがなぜ行動につながらないのか。これも繰り返しになります。物質的欲望にかまけてしまったからです。アダム・スミスが欲望を求めることは正しいと言った。一人ひとりが自分の欲望を最大にしようとすることで、全体がプラスになると言ったわけです。肉屋がおいしい肉をつくる、ワイン屋がおいしいワインをつくる、それらは慈善でやっているのではない。それで儲かるからやっている。みんな金を儲けようとして、おいしい肉をつくり、おいしいワインをつくる。だからみんながそれを買って楽しみ、生産者の利益があがって、更なる次の投資ができる。だから欲望に従うことは良いことだ。みんなが得するんだ、というのがアダム・スミスの理論ですね。これは、理念体系としては正しい。車で言うところのベンツのメカニズムも同じですね。これが資本主義の精神となった訳です。
しかし、人間は必ずしも正直ではありません。理論の通りに機能できません。みんな悪巧みをします。科学技術がいろいろな問題を一時的に解決してきたということもあって、誰もこのシステムの運用の仕方に疑問をもたず、いつの間にか、経済成長が当たり前、成長することが正しいという固定観念が出来てしまいました。ですので、脱成長というのはあり得ない、ということになってしまっています。「足るを知る」という言葉はもう聞かなくなりました。欲望と思い上がりが人間が本来持っていたはずの共感・協調・モラルを凌駕していってしまったと言えるかもしれません。ヨーロッパにいる人も感じていると思いますが、西洋は素晴らしい思想体系をつくりましたが、さっき言った普遍主義・進歩主義・物質主義・科学主義、そして人間と自然が別だとする二元論、そういったものは、自然の摂理、生態系・物質循環・食物連鎖などに実は反しています。それを科学技術の力で押し切り、ここまで文明をつくってきました。そういうものがこれまでの人間行動の座標軸だったと言わざるを得ない。つまり経済成長が目的を達成する、問題が生じたら科学技術の進歩で解決できるというのが、これまでの座標軸だったのです。
素晴らしい人間の理念というかモラルというものがありますが、実は、それは、ドーパミンには負けてしまいます。
ここで、もう一度進化の歴史を振り返ってみましょう。ビッグバン、エントロピーから始まり、認知革命、農業革命、産業革命がありました。人間が認知革命よりも前、ホモサピエンスになった頃、あるいはそれより少し前に戻り、考えていきます。
アンデシュ・ハンセンの『スマホ脳』という本が今流行っていますね。テレビでも取り上げられています。この書籍からヒントを得たことですが、人間の感情を司り、そしてそれを行動につなげるのは、HPA系(視床下部・脳下垂体・副腎系)というシステムです。脳の奥にあり、感情を最優先に扱ってすぐ行動に移す役目をもっている。それはどうしてかと言うと、元々人間というのは、熱帯雨林に住んでいました。そこから草原の方に出て行き、生き延びるために、まず二足立ちを始めました。遠くを見る必要があったから立ったのです。そして、草むらから「ザザザ」という音がしたらライオンかもしれない、ライオンだったら逃げなきゃいけない、あるいは戦わなきゃいけない。ライオンかシカか、何かを真っ先に確認する。ライオンだったら戦うか、逃げる必要があります。シカだったらとっ捕まえて食べます。毒蛇だったら逃げる。最も生存に不可欠な緊急性が高い情報があったら、すぐにそちらに飛びつくというふうに身体が出来ているのです。それはドーパミンという脳内物質を出すことで、全てを差し置いてそちらに注意をやって行動するんですね。似たもので、エンドルフィンというものもありますけれど、エンドルフィンは音楽をきいて「ああいいな」と思うときに出てくる、報酬系のホルモンです。ドーパミンというのは、そういった面もありますが、より重要なのは新しい情報に敏感なことです。この物質に従うことによって、人類はなんとか生存をしてきた、ということです。当時は、10歳までに人口の半分がライオンに食べられるか、毒ヘビに噛まれるか、感染症で亡くなったそうです。それで何とか生き延びるために、新しい情報はまず察知して、そしてそれに即応するということを繰り返してきました。のんびりと食事をしていたり、家族と過ごしていると、食べられちゃうわけですね。したがってそういう即応できる、ドーパミンがすぐ体を動かしてくれる、そういう種が生き残って我々になったということです。
大脳の新皮質に前頭葉という部分があって、そこには記憶を蓄えたり、考えたり、教養を養ったりする力があります。しかし、これはあとから発達しましたから、いざというとき、つまり生死にかかわる問題が発生したときは、HPA系つまりドーパミンに従うことを優先するようになっています。そうすると、スマホが鳴ると「アッ」と手が出る。別にスマホの音に反応しないとライオンに食べられるわけでもないのですが、新しい情報に飛びつけというドーパミンが出てしまうので考える前に反応してしまう。そういうことを悪用しているのがGAFAだとも言われています。行動科学や脳科学の専門家を雇い、着信音が鳴ると手に取り開く、何かおもしろい情報が出てくると次から次へとそこにはまってしまい、余計なものを買わされてしまう。この、HPA系の動きを、いわば悪用しているわけですね。ところが、それがストレスの増大を生んでいるということも書いてあります。詳しくはこのハンセンさんの本を読んでください。最も発達した脳、あとから発達した脳が創った文明には、強い人が弱い人を助けるという正義があります。自分のためだけではない、素晴らしい人間の理念というかモラルというものがありますが、実は、それは、ドーパミンには負けてしまいます。そういうものはそっちのけにして、感情やそれに基づく行動が優先してしまう。したがって理念体系、民主主義や資本主義の素晴らしい理念を円滑に実施することを妨げてしまうのではないか、ということです。
HPAとは、Hが視床下部、Pが脳下垂体、Aが副腎皮質で、この3つが連携することで人間の感情と行動を促すシステムです。そして前頭葉は、知性、教養を扱っている。中でも人間は、認知する力、テクノロジーという前頭葉の部分を発達させたのと同時に、それにアダム・スミスが言っているような、HPA系がもつ欲望を果たそうとする力を組み合わせて経済学、文明をつくったと言えます。ところが、欲望がどうしても暴走をしてしまう。正義・公正を司る前頭葉は、ドーパミンを制御できない、HPA系は前頭葉よりも優先されてしまうので、結局文明がミスマネージされる、折角の知性がちゃんと機能しなくなってしまいます。

文化芸術は、人類が群れの拡大で身を守るために初期に発達させてきた共感力を引き出し、現代のミスマッチを解消する素晴らしいツールにもなります。
知性を身につけるとそうなってしまうことをきっと神様はわかっておられたから、アダムに知恵の実は食うなと仰ったのかもしれません。ところが蛇に騙されてイブ、そしてアダムは食べてしまった。生態系から追放されて、現代のようになった。知性と情動というのは、知性はどんどん発達して高度な文明を創ったけど、情動は一万年前から変わっていないのです。進化というのはそう迅速にはできないらしいんですね。我々が今まで申し上げてきたような、自然破壊、人間同士の戦い、人間のうつ病、そういう悲劇をもたらすことを神様は予測しておられた。だから絶対にあの実は食べるなと仰ったのに、食べてしまった。そうすると、アダムとイブの罪を我々はやっぱり負っているのかな、ということですね。こんなに素晴らしい生態系で仲良く動植物と生きていたのに、知恵の実を食べてしまったが故に、自然を破壊し、人間同士の仲は悪くなり、生きがいも失うことになってしまったのです。
では、どうしたら良いのか。元に、つまり原始時代に戻るのか。それは無理ですよね。逆に、HPA系を進化させようっていっても、ほんの2〜300年の間に始まった近代文明という環境変化に、原始脳が反応してその進化が追いつくはずもありません。あと数千年か、数万年かかるかもしれない。それまで待ってはいられないですね。先に自然が破壊されるか、人類が滅びるかです。
では最後もう一度、進化に立ち戻ってみましょう。京都大学の前総長の山極寿一先生が仰られたことを引用していますが、人類は、最初は弱かった。なんとか肉食獣や感染症から仲間を守るために、ドーパミンで瞬時に反応したり、群れを拡大したり色々の取り組みを行いました。仲間は5人よりも10人、20人、50人のほうが安全だ、敵がきたらパッと誰かが教えてくれる、そうやってみんなで逃げる、子どもをかばう、そうして生き残ってきました。群れが大きくなるにつれ、能力が発達し、頭蓋骨がどんどん大きくなりました。それは、言語を喋るからだと言われているけどそうではなく、仲間の数を増やすためのコミュニケーション能力を増やすために頭蓋骨が大きくなった、ということです。
特にそこで音楽は大事な役割を果たしていると言われます。ゴリラの赤ちゃんは、3年間ほど、お母さんが抱っこしているのだそうです。人間は1年でもう突き放してしまい、離乳食をあげ始めます。なぜかというと、10歳までに人口の半分が外敵や病気、飢餓で死んでしまっていたので、どんどん産まなきゃいけない、3年間も待っていられないわけです。ですので、1年で子どもは離して、お母さんは子どもを産めるようにして、どんどん産んで、人口を保ってきたのです。
その代わり、可愛そうなのは赤ちゃんで、1年間でほっぽりだされてしまいます。つらいから泣きますね。泣くと、お母さんはそばに行ってやれないけれども、遠くからなだめる。高い声で「いい子にしてなさい」「もうじき行くからね」とか「おいしいごはんあげるからね」と言って。それが子守唄に発展したと言われています。世界中の子守唄を聞いてみると、すべてピッチが高く、変化の幅が広く、母音が長めに発音されて、繰り返しが多い、そういった共通性があります。子守唄は、人間の、言葉を使わないコミュニケーションの原点なのです。だから、音楽というのは、生の演奏を聴くと感動し、そして、弾いている人、聴いている人の間に心が通います。そういう能力をちゃんと、人間は発達させてきています。群れをつくって、大きくして、自分たちを守るために、みんなで歌う。合唱や、合奏です。そうすると、音声と動きが同期し、満足感が誘発され、怒りが発散され、感情や信頼が共有されて、境界がなくなる。国境もなくなる、社会が同一化する。そういう共感力を発達させる音楽、文化芸術を、人間は発達させてきています。
そういった文化を守り、これから取り戻すべきではないでしょうか。そうすることによって、共感力が高まり、社会の分断に繋がり兼ねない理念体系と現実のギャップに橋渡しができる。つまり民主主義はこうだ、資本主義はこうだ、だから合理的に行動しろという現代社会の要請について行けない人たちを互いを労りあいながら、協調して守っていく能力というものが、文化芸術によって保てるようになります。アンデシュ・ハンセン先生が言っている、近代文明とHPS系のミスマッチの問題を解決するには、どちらかを動かすのではなく、その間を取り持つ共感力を増やせばいいのではないかということです。そこで、先ほどの非認知能力育成に繋がります。子どもの頃に文化芸術、音楽、演劇をやっておくことで、そういう能力が子どもたちに育まれます。しかも、それにより認知的能力も一層身につくということです。
文化芸術活動が育てる共感力は、自然や動物に対する気持ちや共感度も増します。先ほどの自然の生態系に対する理解も生まれますね。どんな人間にとって都合の悪い生物も、生態系の一部で大事な物質循環やっているんだ、だから自分が嫌いだからといって殺しちゃいけない、ということです。ゴキブリは気持ち悪いけど、役割があるのだから理解しよう。うちも2~3日前にネズミが出たんですけど、ネズミにもちゃんと役割があります。ミミズもそうですね。人間は自分勝手なので、気持ちの悪いものは害虫、害獣、自分が好きなもの、都合のいいものは、益虫、益獣といって可愛がります。自分が嫌いなものであっても、共感を持つこと、そうすれば自然破壊は減っていきます。加えて、文化芸術の活動は、天然資源をほとんど収奪しません。音楽、作曲するのに、演奏するのに石炭や石油は使いません。
共感力が増せば、民主主義もよりよく機能します。アメリカの哲学者であるマーサ・ヌスバウム先生はこう言っています。今、経済成長が全てで人文系は駄目だと言われている、無駄と言われている。しかし、実際はそうじゃない。人文学と芸術をしっかり社会に浸透させることで、共感力が増す。共感力が増してはじめて民主主義が機能する。選挙で負けたら不愉快だけど、我慢できる。同じように国のために尽くそうとして、あいつが票をとったのだから、まあ我慢しよう。経済でも、ライバルに負けた、悔しい、でも嫌がらせはしないで、自分は頑張って、共に企業活動を通じて社会に貢献しよう。そういう気持ちがベースにあれば、勝ち負けも受け入れられるはずです。
文化芸術は、人類が群れの拡大で身を守るために初期に発達させてきた共感力を引き出し、現代のミスマッチを解消する素晴らしいツールにもなります。それこそこれからの人類社会を運営していく上での新しい座標軸になります。大局観をもっていろいろ昔を振り返り、出てきたひとつの結論です。座標軸は経済成長じゃなくて、共感力にしようということです。

経済に代表される文明文化を経済に合わせるのではなく、経済を文化に合わせる。文化の活動方式がちゃんとビジネスになるような経済の仕組みを考えることが大切です。
これから文化芸術経営を皆さんなさるわけですけれども、そこでぜひ心に置いていただきたいのは、文化芸術と経済(少なくとも現在の経済の仕組み)は、そもそも親和性が低いということは認めざるを得ないということです。文化は経済価値ではなく、個人や社会の質を高めることを価値とするわけだから、相容れないのは当然だ、と考えることが大切です。したがって、利益、報酬、事業の定量化、市場拡大、大量生産によるコストダウン、使い捨てによる買い替えの奨励、それからマーケティングのように、経済では常識になっていることに、引きずられてはいけないと思います。文化の本当の価値を失ってしまうからです。
文化を経済に合わせるのではなく、経済を文化に合わせる。文化の活動方式がちゃんとビジネスになるような経済の仕組みを考えることが大切です。非物質的な、定性的な価値の取引ができるような工夫、そういったものを考えていく必要があると思います。例えば、文化芸術活動が経営判断の対象になりやすいような工夫、例えば消費者にもっと文化芸術の価値をわかってもらうことです。需要があれば経済人は動くわけですから。そして、伝統工芸の作家さん、なかなかプロダクトアウト主義なので「いいものつくりゃいいんだ」「世論におもねるのはとんでもない」と思っています。しかし、ある程度マーケットインをしなければ、物は売れない時代です。したがって、プロダクトアウトを主とする作家と、マーケットインがわかっている仲介者、プロデューサーのような人材が生まれれば、文化はその質を守りつつ今の経済のメカニズムに入りやすくなると思います。
そして非認知能力の強化ですね。私はこれからお稽古ごとの塾でもはじめようかとも思っている位で、塾で算数やプログラミングを習わせるのではなくて、お稽古ごとをやらせるということが文化芸術への需要を高め、文化芸術経営者にとってのビジネスチャンスになりますね。また、これからはシェアエコノミーの時代になりますから、リサイクルショップが流行します。今、美術・工芸品のリサイクルショップはありません。「あんな素晴らしいものがタンスに眠っている。それを出してきて、もっとみんなでシェアできないか」ということがよく言われています。文化の価値を低めずに、経済の仕組みを少し拡大することで、なんとか、そういう新しい座標軸をつくっていただきたい。
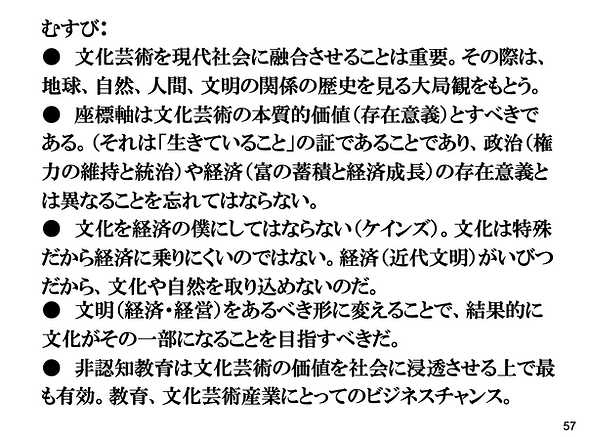
経済に代表される文明全体を、あるべき形に変えることで、文化と一体となるというところを目指すべきだと思います。
ここからは復習です。まず、文化芸術を現代社会に融合させることは重要。しかし、地球、自然、人間、文明といったものの歴史を見る大局観は常に持つ必要性がありす。他方、自分の行動基準となる座標軸はやっぱり文化芸術の本質的な価値に置くべきです。それは生きていることの証だからです。例えば、小説は時間をかけ苦労して主人公になりきって読むということに価値があり、あらすじを読むだけでは意味がないということですね。したがって、政治や経済の存在意義とは違うということは忘れてはなりません。「文化を経済のしもべにしてはいけない。」イギリスのアーツカウンシルの初代の理事長であるジョン・メイナード・ケインズの言葉です。工夫をして、妥協はするなということですね。文化と経済の相性が良くないのは文化が悪いのではなく、経済が歪なのだということをしっかりと覚えておいていただきたい。経済に代表される文明全体を、あるべき形に変えることで、文化と一体となるというところを目指すべきだと思います。その上で、そういう気持ちを持つ人が増えるためには、やはり、幼児教育において、文化芸術の価値を教える、体感、体験させるということが、極めて重要です。ビジネスチャンスをつくるということは、まずはそこから始めるべきではないかと思います。
日本文化の特徴とは「自然との関係性」。
実は、そういう観点から日本文化は素晴らしいということについていくつか資料を持ってきています。それを最後にご紹介出来ればと思います。私がいつも言っているのは、日本の文化の何が一番特徴かと言いますと、自然感、自然との親和性です。アインシュタインが相対性理論を説くために日本に来た時の記録がありますが、そこで彼は、日本では自然と人間は一体化しているように見える、この国に由来するものは全て愛らしく、朗らかであり、自然を通じて与えられたものと密接に結びついています、と言っています。
レヴィ・ストロースという有名なフランスの文化人類学者もこう言っています。日本では「はたらく」ということを、西洋式の生命のない物資に対する人間のはたらきかけではなく、自然との間にある親密な関係の具体化であり、人間にとって働くということは、そういうことである、と言っています。これはさすが人類学者、名言ですね。農作、例えばトマトをつくるということ一つとっても、これはトマトという物質をつくって高く売るために作っているのではなく、自然を愛し、土を愛し、気候と一体となりながら、トマトを手塩にかけて育てる。ここに心が通っている。そのトマトを可愛そうだけど売ってしまう。その経験を糧にして、また次のトマトを作る。人が本来はたらくということはそういうことで、自然と一体になる、そのやりとりにあるんだということを、彼は短い滞在の間に悟ったんですね。
現在コロナで中断していますが、日本美術協会が主催する、高松宮世界文化賞という、文化のノーベル賞と言われているものが秋にあります。数年前、そこで賞を受けたイタリア人の建築家が招かれていて、彼は日本の文化をよく理解しているという紹介もあったので「あなたは日本の文化の特徴を一言で言ったらなんとおっしゃいますか」と聞いたら”Relationship with Nature”と言いました。まさに自然との関係性だと言う。日本文化の価値を理解する人はみんなそう見ているのだと気が付きました。日本人は当たり前だから感じないことも、外から見ると、特にヨーロッパから見ると、日本人って本当に自然と一体になっているなぁと感じるわけですね。

それから、この須佐之男命厄神退治之図という、北斎が1845年に描いた絵があります。当時も疫病がたくさんありました。これは、それらを須佐之男命が退治に来ている絵ですね。ペストとか、コレラとか、結核とかいろんな病気が、ここでは鬼として描かれています。それらをやっつけて、もういい加減に悪いことやめろ、と言っているわけです。中でもペストであるらしい鬼(絵の左下)が「わ、わかりました」と、言って、この連判状に自分の手形を押している。つまり、須佐之男命はこの鬼たちを殺すんじゃないんです。悪魔を追い払う、厄払いというふうにしています。いくら人間にとって都合が悪くても殺しはしない。向こうに行っておけ、お前にはお前の役割がある、ということで絶滅させないんですね。どんなに嫌な相手でも、どんな自分に都合の悪いものにも、共存する価値がある、と根本的にわかっている。そういう多様性があるからこそ、生態系は回っているわけです。多様性がどんどんとなくなっていけば、例えばですが、ある雑草とあるシマウマとあるライオンだけしかいなかったら、環境変化が起こり、どれかが絶滅すれば、簡単に生命体は潰えてしまいます。そうなってはいけないということが、日本人には本能的にわかっていたのではないかなと思います。
もちろん、作品のみならず、生活の中にあるものもそうですね。年中行事ですとか、方言というものにも、本当に微妙な季節というものを、あるいは人間関係を表わす、独特な表現があります。和歌や、俳句、茶道、華道、香道も、季節季節の意味、つまり季節感、他の動植物を含む全てのものへのいたわりに満ちています。

例えば、同じ庭をつくるにしても、日本とヨーロッパでは特徴が異なります。左は岩手県の毛越寺の庭園です。平泉の世界遺産の一部です。右はパリのベルサイユ宮殿の庭、どちらも素晴らしい庭ですが、どちらがほっとするでしょうか。私は毛越寺の方ですね。ベルサイユの方は、円があって、直線があって、左右対称です。毛越寺の方は全くそういったものはない。左右対称とか完全な円、直線的なものというのは、幾何学的な抽象的な概念です。円とは、ある点から、同じ距離にある点の集まり、理屈はそうだけれども、自然にはそれは存在していません。直線も二つの点を結ぶ最短距離、理論はそうだけれども、同じく自然には存在していません。だからこそ日本の庭にはそういったものがありません。ヨーロッパは、自然にないものをつくれることを人間の優れた能力として誇りに思い、それが芸術にも現れている。ベルサイユの庭を批判しているわけではありませんが、ここが日本と西洋の文化の違いです。西洋の概念に、もう少し日本の文化の深さを混ぜることによって、その双方をうまくつないでいけるのではないかと思っています。

日本語に残る日本人の思想の深さを取り出しつつ、今日のとりまとめをしましょう。
自然に従うという点で言えば、例えば、ヨーロッパでは噴水は高く上にあげますね。水の芸術です。高く上げればあがるほど素晴らしい。人間は自然とは違う、自然を超越している、だから偉い、だから引力に逆行して水を上にあげられるんだ、というのが噴水芸術です。日本の庭では、水は、絶対に上から下へ流れますね。踊りもそうです。バレエは引力に逆らって高く跳ぶことが美しい、日本舞踊は地に足をすりこんで、沈み込むように踊ります。地面に対する敬意、地球に対する敬意の現れです。
もう一つ、『羽衣』という謡曲があり、お能にもなっていますね。あれは、三保松原の話です。その中に次のような台詞があります。白龍という漁師が、羽衣を見つけ、持って帰ろうとしますが、そこに羽衣の持ち主である天女が現れて、返してください、私のものですと言います。押し問答の末、最後に漁師は返してやろうと思い至りますが、返す前に天女の舞を舞ってくれと言います。天女は、わかりましたと承諾しますが、その羽衣がないと舞は舞えません、と言います。すると、漁師は、じゃあ駄目だ、お前は嘘をついて、羽衣を渡した途端に帰ってしまうだろう、と言いました。そうすると、天女が言います。「いや疑ひは人間にあり。天に偽りなきものを」相手を疑うのは人間だけです。天では嘘をつきませんという意味です。それを聞いて、さすがに漁師は、人間というものの恥ずかしさを知り、じゃあ、と言って羽衣を返すんですね。そういう話がもう600年も日本に残っています。
最後に、日本語に残る日本人の思想の深さを取り出しつつ、今日のとりまとめをしましょう。まずエントロピー増大の法則とは、物事、環境は常に壊れる、秩序は変わるというものでした。日本人はそれを感じているからこそ「驕れる者久しからず」という平家物語の冒頭の文言になるし、物質循環、つまり炭素がぐるぐる回っていうところは「金は天下の回りもの」という言葉はまさにそれを表しています。伝統工藝の素晴らしさは、素材を自然からもらい、色を自然からもらい、大事に使って修復して、最後は土に返る、ということですね。食物連鎖に欠かせない相互依存の重要性についても「三方良し」という言葉がありますね。企業を興すときに必要な考えです。自分だけではない、社員もクライアントも大事、ステークホルダーもみんな良くしていくという考えですね。「足るを知る」という言葉もありますよ。今の人間は足るを知らない、限りなく稼ぐことだけを考える、しかし、もともとは「足るを知る」という考えが日本にはあり、欲望を野放しにすることへの抑制感があったわけです。渋沢栄一もそういったことを言っていますね。そして多様性の受容、これはつまり嫌なものとの共存でもありますね。須佐之男命厄神退治之図でお話したことです。そして動的平衡、「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。淀みに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし。世の中にある人とすみかと、またかくのごとし」鴨長明の『方丈記』にありますが、物事は固定していない、人生もここで言う「よどみ」なんだと。「一期一会」も同じです。今日の自分は昨日の自分と違う、生物学的には実際違うわけですよ。入れ替わっているわけですから。そういうことを、文化の中で、直感で感じていることなのではないかということがわかりますね。
少し長くなりましたが、ここまでということで。是非、皆さんと色々な意見交換が出来ればと思います。ありがとうございました。
Cultural Innovation Leadership 基調講演
近藤誠一氏 2021年6月15日

